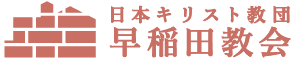説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2018年2月25日
「羊と鋸」 ローマの信徒への手紙03:21〜26
古賀 博牧師
〈聖書〉
|
21:ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。22:すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。23:人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、24:ただキリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。25:神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは、今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。26:このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、御自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。
|
|---|
今日は、ローマの信徒への手紙3章の後半部分を読んでいただきました。パウロが「信仰義認」を語っている箇所で、代々の教会においてとても大切にされてきました。さらにこの箇所を通じて、マルティン・ルターが「信仰義認」を改めて確信し、宗教改革へと向かっていく力を得たことでもよく知られています。
昨年(2017年)は宗教改革500年の記念の年でした。宗教改革の出発は1517年10月31日。この日、マルティン・ルターがヴィッテンベルグの城教会に95ヶ条におよぶ提題を掲げたのです。「95ヶ条の提題」と呼ばれ、これは当時のローマ・カトリック教会に対しての公開質問状でした。
16世紀のはじめ、ローマ教皇レオ10世はサン・ピエトロ大聖堂の建築資金を調達するため、贖宥状(免罪符)の販売を強力に推進しました。最も大々的に販売されたのはドイツ。ドミニコ修道会から派遣されたテッツェルは、「お金を箱の中に投げ入れ、チリンと音がするとともにあなたの魂は救われる」と語り、人々に購入を勧めたとのこと。当時の教会は、死者は天国への道筋で煉獄に留め置かれ、そこで罪の精算が為されて、初めて魂の救いへと至れるのだと教えていました。煉獄での精算が容易になり軽減される、と説いて贖宥状が販売されました。
ローマ・カトリック教会のこうした行き過ぎたあり方に疑問を呈したのが、当時、ヴィッテンベルク大学の神学教授であったマルティン・ルター修道士でした。
彼が城教会の扉に掲げた提題の第一はこう始まっています。“わたしたちの主であるイエス・キリストが、「悔い改めよ」と言われた時、彼は信ずる者の全生涯が悔い改めであることを欲したもうたのである”。
ルターは、このような短文の提題が95も並んだ一枚の大きな紙を、「万霊節」(現在のプロテスタント教会はその日を「召天者記念日」としていますが)の前日である10月31日に、多くの人々がミサに集っていた有名な教会の壁にラテン語で記して張り出したのでした。
この提題の内容は、その後、すぐに多くの人々が読めるドイツ語に翻訳されて、たちまちドイツ中に広がり、さらにヨーロッパ全土でも大きな反響を呼び、宗教改革運動の引き金となりました。
ルターを突き動かした原動力は、3章23〜24節にあるみ言葉でした。
「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです」。
ここから導かれた「信仰義認」の確信、それがルターの力の源となったのです。
○新しい時代の始まり
21節から22節を見ていただくと、「ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません」と記されています。
21節の「ところが今や」という言葉が重要です。これは、いまこの時に全く新しい時代が始まったのだ、とのパウロの力強い宣言です。どんな時代が始まったというのでしょうか。
前回の説教で取り上げたのはローマの信徒への手紙の1章でした。その際、ご一緒に学んだように、1章17節までがこの手紙の書き出し部分に当たります。書き出し部分で、パウロは自己紹介を行い、続いて自らの福音理解を短い言葉で示しました。「福音を恥としない」という語り出しで始まっていた16節から17節ですが、そこにパウロはこの手紙の中心的な使信を置いたのです。
続く1章18節から、今日の3章21節の直前に至るまで、ごく簡単に申し上げれば、全ての人は神の前に罪人であるということが書き記されています。
イスラエルには、神との契約において、御旨に生きる指針として、本来は恵みである律法が与えられていました。この律法を通じて神の御心は確かなものとされ、人間は律法を守ることで神と深い結びつきを得て、救いへと至ることができる、これが旧約的な信仰の道筋だったのです。
律法の中心であるモーセの「十戒」、これが与えられたのが概ね紀元前1200年、その後の長いイスラエルの歴史の中で、民たちは律法に忠実であろうと努めながらも、それにことごとく敗れ、偶像礼拝に陥り、律法を守ることができず、神と人との契約関係は破綻していきました。
その結果としてのバビロン捕囚、その後に律法と言葉による礼拝を中心として信仰の組み立て直しが行われました。ところが、今度は律法に集中するがあまり、律法主義というものが登場します。律法の条文にとらわれて、一言一句に拘泥するようになり、律法学者による恣意的解釈などが、人々をがんじがらめに縛り付けるようになります。神との関わりを整えるために恵みとして与えられたのが律法ですが、その本質はいつしか廃れ、神の名の下に人間が人間を縛り、管理するために律法は機能するようになっていたのです。
こうした状況の最中に、御子イエスが出現し、その福音、十字架と復活とによって、これまでとは全く違った新しい世界・時代が出現した、この出来事をパウロは21節以下に語り出しました。この大いなる変化を、パウロは「神の義」という表現で明らかにしているのです。
もう一度、21〜22節を読みます。
「ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません」。
○「神の義」とは
ここで語られている「神の義」からも学びたいと願います。
「神の義」とは旧約聖書においてツェデク、またはツェダーカーという語で、意味は「まっすぐであること」「正しい状態にあること」です。新約聖書ではギリシャ語でディカイオシュネー。このディカイオシュネーとは罪の対立概念で、意味はやはり「正しい状態にあること」。まっすぐで正しい状態、これは神と人との関係、結びつきが正常な形に整えられたことを語っています。
パウロは、旧約聖書の時代から、律法によってはついに到達し得なかった「神の義」、神とのまっすぐで正しい関係が、イエス・キリストにより、この方を信じることで実現されるのだとし、その理由を続く23〜24節に語っています。
「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです」。
イエス・キリストの死、それは神が御子イエスを代価として捧げてくださったことで、この出来事をもってはじめて人間は神との正しい状態へと導かれる、この神の恵みをパウロは宣べ伝えています。25節に「神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました」とある通りです。
人間は自らの業をもっては神との関係を整えることはできない、それはただ恵みとして神の側から与えられるもので、そこにイエス・キリストが十字架上で血を流して死んでくださったことが深く関わっているというのです。
○「義」という漢字
神学者の北森嘉蔵さんは、「義」という漢字に注目して、この箇所を解説されています。
義とは、羊と我という字が上下にくっついてできています。上は「羊」です。下の「我」は私という一人称を意味する字ではなく、武器の「戈」(ほこ)を表す象形文字が原形、これにギザギザとした鋸状の刃を付けた象形文字が「我」という字だというのです。
「義」の旧字体は「羲」。白川静さんの『常用字解』によると、犠牲にする羊を鋸で切り分けた際、祭壇の下に羊の後ろ足が垂れている形だ、と解説されています。
このように「義」は、羊を自らの代わりに神への捧げものとして鋸で切り開き、その命を犠牲として捧げることで、神との関係を整えようとしたことを表す字です。
「犠牲」という字にも「義」が入っていますが、これは羊のみならず、牛も生け贄としたこと、「牲」は牛を生きたまま生け贄としたことを表しています。
漢字の背景にあるのは古代中国の宗教行為でしょうが、これと同じく犠牲の献げ物は、旧約聖書時代、神殿祭儀においても重視されていました。後に神殿が崩壊し、祭儀は、動物犠牲ではなくて、律法を中心とした礼拝行為へと変遷します。
これらの宗教的な変遷の全てを乗り越え、全ての人の罪の贖い、誰もが与ることのできる救いを完成させるために、イエス・キリストの十字架での死、そこで流された血があったのだ、これが23節以下に語られているパウロの信仰です。
○神は御子を、あるいはご自身を献げる
先に語った、「義」、あるいは「犠牲」という字の語源にもありましたように、過去以来、人間は羊や牛を自分の代わりに捧げて、神との結びつきを整えようとしたり、神から赦しや祝福を得ようと祈り願ってきました。こうした意味合いで、旧約聖書の信仰においても、自らの罪の身代わりとしての動物犠牲が重んじられていたのです。
しかし、この宗教的あり方をキリスト教は大転換しました。招詞としたヨハネによる福音書3章16節に「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」とある通り、神は愛の故に大切な独り子をこの世に送り、その御子を十字架の上で死なせ、贖いの犠牲とされました。これは神が人間のために、愛する御子を捧げたこと、さらに言えば自らを犠牲とした行為であると受けとめられています。
人間の方が神の御前に犠牲を献げる、これが通常の宗教のあり方です。「義」や「犠牲」という漢字の成り立ちもそれを表しています。ところが、キリスト教では全く逆のことが起こっています。神が御子を、もっと言えば神ご自身を献げて、人間を執り成し、贖い、救いへと導こうとされたというのです。
これをパウロは「神の義」と表現しました。これほどまでに神から先んじて示されている愛と贖いを深く感謝して受けとめる、そこにキリスト教の真実の「信仰」が出発していくのだと、パウロは宣べ伝えています。
○「神の義」への応答
最後に、「神の義」「信仰義認」に応答していくあり方について、パウロが述べている箇所を確認したいと思います。ローマの信徒への手紙の12章1節です(新約聖書291ページ)。
「こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなたがたに勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえとして献げなさい。これこそ、あなたがたのなすべき礼拝です」。
神自らが、御子であり、自らと何ら変わりのないイエス・キリストを犠牲として捧げられた、このことの応答として、キリスト者は「自分の体を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえ」として献げるようにと勧められています。
自らを羊を鋸で切り分けたような血なまぐさい犠牲として祭壇に献げよ、というのではありません。神に贖われ、救われた者として、喜びと感謝をもって日々の生活にキリスト者として生きよ、との勧めです。キリスト者として、こうしなければならない、こうしてはならない、そんな縛りや律法から完全に自由になって、神が喜ばれるあり方へと活き活きと進んでいく、それが「自分の体を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえ」として献げること、それが「なすべき礼拝」だと言うのです。与えられている大いなる神の恵みに気づいて、それを感謝して受け入れ、真実な「礼拝」への歩みを、それぞれのあり方・生き方で進んでいきたいと願います。