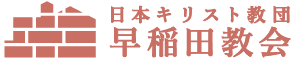説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2018年3月11日
「たとえ明日」 ローマの信徒への手紙05:01〜05
古賀 博牧師
〈聖書〉
|
1:このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、2:このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています。3:そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、4:忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。5:希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。
|
|---|
1節から2節を再度読みます。
「このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています」。
1節に、パウロはその信仰の確信を記しています。律法に破れ、人間の力をもってしてはどうしても神の御心に生き得ないとの罪を負っている私たち。そうであっても、主イエス・キリストの十字架の贖いによって罪赦され、この主イエスを信じる「信仰によって(こそ)義とされ」ています。
この「神の義」がこの手紙の中心的な使信であり、律法に破れ去り、神との契約の責任的相手となり得ない私たちに、神自らがその御子を、またご自身を捧げることで与えてくださった大いなる恵みだと、先般、3章から共に確認しました。
そして、この神の大いなる恵みによって、主イエスの十字架とその贖いとによって、神から切り離されていた私たちは改めて神と和解することを許されているのです。この状態を、パウロは「平和」と表現し、「神との間に平和を得」たのだとここに宣べ伝えています。
続く2節に、「このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ」とあります。ここは以前にもお話しましたが、「今立っているこの恵みに入る、その入り口を私は手に入れている」という不思議な表現となっています。
カール・バルトは『ローマ書講解』において、ここを「もちろんかれにより、われわれは今立っているこの恵みに入る入り口を信仰によって与えられた」と訳しています。岩波訳聖書では、「そのイエス・キリストをとおして私たちは、信仰によって恵みへと至る路を獲得しているのであり」との訳になっています。
これらの訳語を通じて知らされるのは、パウロは神の恵みを実感しつつ、なお信仰を深めて本物とするために、“入り口”に立っている状態から新たに歩み始める必要を説いているということです。あるいは、真実で揺るぎない「希望」へと到達するために、神から示されている信仰の“路”へと一歩を踏み出そうと励ます、そんな語り方をパウロはここでしています。
○希望への道筋
真実の希望へと到達する路はどのように続いているのでしょうか。3節以降にこうあります。
「そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを」。
真実な希望への路は「苦難」から「忍耐」へ、「忍耐」から「練達」へ、「練達」から「希望」へと続いているのだというのです。「苦難」「忍耐」にとどまらず、それが「練達」、ついには「希望」へ繋がっていく、この神の約束は、多くの人々を強く励ましてきました。自分の体験に照らしても、このみ言葉の力を思います。
パウロが語る「忍耐」とは、消極的にただ耐え忍ぶのではなく、果敢に「苦難」と闘い続けるあり方です。ここには“勇気”とも訳せる言葉が用いられています。
「練達」とは、金属を火に通して精錬していくこと。このように何度も火にかけ不純物を除き、金属を純粋で強固なものへと導いていくあり方が示されています。
このように鍛えられていくものとは何なのか、これを福音派が用いる新改訳聖書では「練られた品性」と訳しています。その人の内面が鍛えられ、広く・深く・あたたかい、人に快く響き伝わる品性へと繋がっていくということでしょう。
そして5節にあるように、「わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているから」、この信仰の道筋を辿ることにより、私たちは神によて確実な「希望」へと導かれる、このことをパウロは信じて語っています。
「苦難」から「忍耐」へ、「忍耐」から「練達」へ、そして「練達」から「希望」へと進んでいくと宣べ伝えられています。こうした信仰の道筋を信じて、神の寄り添いを祈り、入口から一歩を踏み出していく、このことこそが励まされています。
とかく私たちは自らの弱さの故に、進みゆくその先が途方もない「苦難」の連続かもしれないと怖じ気づき、最初の一歩をなかなか踏み出せないでいます。入口のところでうろうろしている、そんな自分があります。そうした自分を反省し、どれほどに小さく、また徒労にしか思えない歩みであるとしても、信仰による一歩の踏み出しが大切ではないでしょうか。
実際に、「苦難」から「忍耐」へ、「忍耐」から「練達」へ、そして「練達」から「希望」へと神の御手に頼りつつ、聖霊の支えを受けて進んでいく、こうした信仰が今の私に、そしてまたこの時代を生きていく一人ひとりに強く求められていることを思います。
○3.11から7年を迎えて
本日は3月11日、東日本大震災からちょうど7年目です。2011年の3月11日(金)午後2時46分、ここに集うお一人おひとりにさまざまな体験があり、あの激震の衝撃と恐怖、そして報道を通じて流された大津波の映像、全てを破壊し、飲み込み、流し去る圧倒的な黒い波の姿が、瞼に焼きついて離れません。
その年の6月、千代田教会の太田春夫牧師(東京にお出でになる前は、長く新生釜石教会で奉仕された方)の案内で各被災地を2泊3日で巡りました。
3ヶ月という時間が経過し、岩手県沿岸部では遺体の収容や瓦礫の撤去が急ピッチで進められ、市街地はどこもすごい粉塵、また匂いに満ちていました。
陸前高田市、海岸線から高台までに鉄筋コンクリートの建物の残骸が幾つか残っており、後は水たまりという荒れ地になっていました。西側の傾斜地では、自衛隊員たちが遺体捜索を行っており、所々に死者発見の赤いリボン標識が風に揺れている、何とも言えず荒涼とした風景・光景を忘れることはできません。
あれから7年、それぞれの被災地はどうなっているのでしょうか。この間の報道を通じて、7年が経っても復興の道筋が明らかでないこと、当初の予定にはさまざまな狂いも生じ、痛みは継続し、さらに深くなっていると知らされています。被災地に生きている人々の苦しみ、これを改めて想像しています。
東京教区北支区は、奥羽教区との交流を進めている中で大震災を経験し、岩手県の支援に集中しました。その後、福島にはさらに深刻な課題があり、原発事故、放射能被害の現実とも向き合おうと、支援と交流の方向を福島へも広げました。
岩手・宮城の沿岸地方とは異質の被害が、福島に、特に福島第一原子力発電所から半径30キロ圏内、また風に乗って原発から北東方向に高濃度の放射能が拡散した地域にあることは、皆さんもよくご存じの通りです。
○“希望”の牧場
先週の木曜日に本屋にて、『牛と土−福島、3・11その後』という本を見つけました。眞並恭介さんというノンフィクション作家のルポルタージュで、2015年に単行本として出されたものの文庫版です。
裏表紙の内容紹介の言葉の一部を読みます。
「東日本大震災、福島第一原発事故で被曝地となった福島。警戒区域内の家畜を殺処分するように政府は指示を出した。しかし、自らの賠償金や慰謝料をつぎ込んでまで、被曝した牛たちの〝生きる意味〟を見出し、抗い続けた牛飼いたちがいた。牛たちの営みはやがて大地を癒していく−そう信じた彼らの闘いに光を当てる…」。
とても印象的な紹介文です。
今日の話の準備をしながら、私は心に、一つにはジャン・ジオノの『木を植えた人』の物語、そしてもう一つにはルターの言葉を置いていました。
最初の『木を植えた人』は、フランスのプロヴァンス地方の荒れた高地で、独りドングリを地中に埋め、その地に森を作り出そうとする羊飼いの物語です。独りの羊飼いが幾多の困難を越えて、地道な作業を続け、森を作り出し、それがついに何に繋がったかを描いた小説。この小さな物語を通じて、今日のパウロの告白の現実を見る思いがします。「苦難」から「忍耐」へ、「忍耐」から「練達」へ、「練達」から「希望」へと続くという路、その道筋を証しているような物語です。
『牛と土』、手に入れたばかりなので斜め読みですが、この本に記されている牛飼いたちの取り組みに、『木を植えた人』のメッセージと同質のものを感じました。
汚染された土壌に育つ草を食む、殺処分を逃れた被曝した牛たち。決して出荷できない牛たちを守って、殺処分ではなく、牛としての生涯を全うさせてやりたいと奮闘する牛飼いたち。家畜・人間、双方のいのちを大切にするあり方、また放射性物質が土→草→牛→糞という循環で次第に除かれていくことに注目し、牛を飼い続け、地道に除染する可能性に期待をかけ、いつの日にか土壌が浄化されることを祈りながらのさまざまな取り組みが、浪江町で続いているというのです。
こうした牧場の一つが「希望の牧場」。そこには300頭もの被曝牛が飼育されています。この「希望の牧場」の働きは、非営利の一般社団法人化され、志を同じくする日本中の方たちの支援を受けながら、今も続けられています。
ある牛飼いは、100年後も牛も農作物も出荷は難しいだろう、でも浪江町に「桜の園」を作り出そうと、桜の苗木を植え続けているとのこと。ソメイヨシノよりずっと寿命の長い枝垂れ桜、500年から1000年は保つというこの桜を植え、下草を被曝牛に食べさせて、土→草→牛→糞の循環を生み、樹木管理を続けているというのです。ただ絶望しない、いつかは希望が実るかも知れないと信じて、殺処分を命じられた牛たちのいのちと力を活かしている、そんな牛飼いもあります。
○たとえ明日
“たとえ明日この世が滅びるとしても、われわれは、今日、われわれのリンゴの若木を植えようではないか”。
これはルターが語り残したと言われる言葉です。
ルターは、この世界が明日滅亡するとしても、また自分の人生が突然中断するとしても、今何をしなければならないかを見定めていました。それは、リンゴの若木を植えるという行為です。
リンゴの若木とはキリスト教的には希望の象徴です。いつか希望が実るであろうと信じ、それまでに実に長い年月が必要だとしても、この世に希望が芽吹き、実るための働き、いつの日にかこの世に自由と解放の神の国が到来すると信じて、諦めることなく祈り・奉仕し、与えられた今日を神の御旨に生きる、このようなあり方を、ルターは“たとえ明日この世が滅びるとしても、われわれは、今日、われわれのリンゴの若木を植えようではないか”と語り継いだのです。
東日本大震災の被災地は、今この時も厳しさの中にあります。岩手・宮城・福島、あるいは千葉、そして内陸部、それぞれに課題があります。そのような被災の現実を忘れることなく、冷静に見つめ、学んでいきたいと思うのです。
私たちは自らの問題・課題だけに埋没することなく、この世界の現実とも闘いながら、「苦難」から「忍耐」へ、「忍耐」から「練達」へ、そして「練達」から「希望」へと信仰の道筋を進む、祈りつつこの一歩を踏み出していきたいと願います。