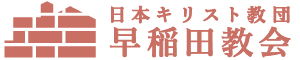説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2018年5月13日
「混沌に差す光」 創世記 1:1〜5
古賀 博牧師
〈聖書〉創世記 1:1〜5
| 1:初めに、神は天地を創造された。2:地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。3:神は言われた。「光あれ。」こうして、光があった。4:神は光を見て、良しとされた。神は光と闇を分け、5:光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。 |
|---|
○「創世記」という文書名の変遷
今日読んでいただいたのは、「創世記」の冒頭部分です。
旧く、本のタイトルとは、その書き出しで表すのが通例で、この「創世記」も冒頭の言葉で言い表されてきました。この書の最初の言葉は、ヘブライ語の「ベ・レーシート」、「はじめに」という意味を持っている言葉です。これに従い、この文書は「ベ・レーシート」=「はじめに」と呼ばれていました。
後にギリシャ語に移し替えられますが、2章4節の「これが天地創造の由来である」とのみ言葉からGenesisと翻訳されました。Genesisとは「起源」を意味しており、この言葉で文書全体が言い表されるようになり、今日を迎えています。
この文書は神による世界の創造から語り始められ、この世の起源が記されています。世界の創造に始まり、続いて人間の創造、最初の人間たちの生活、その子たちの時代の問題などなどを、「創世記」の天地創造の物語は描いていきます。
いわゆる神話的な記述は、「創世記」の11章まで続きますが、これらの物語から、キリスト者たちは、自分たちが信じている神はどのようなお方であるのか、この世界はどのように造られ、始まっていったのか、人間とはどのような存在なのかなどを、神の御心、神からのメッセージとして聞き取ってきました。
○バビロン捕囚の現実の最中で
今日の箇所、2節に「地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた」とありますが、これは自然現象について言い表しているのではなく、こう記した人々の直面していた現実を表現しているものです。
「混沌」とはカオス、これは全てが破壊し尽くされ、形を失い、無秩序となってしまっている状態です。「混沌」(カオス)と表現せざるを得ない厳しい現実を、「創世記」の1章を記した人々は実際に目の当たりにしてのでした。
この「創世記」の1章が書かれたのは、紀元前6世紀であろうと言われています。「創世記」は幾つかの時代背景の違った資料によって構成・編集されていますが、1章には、紀元前6世紀、バビロン捕囚の時期に編纂されたのであろう「祭司資料」と呼ばれているものが用いられています。
バビロン捕囚とは、イスラエル史上、最も困難な時代・状況でした。
捕囚に至るまでの王国の歴史の概要を確認しておきます。大体紀元前1000年頃にダビデが王位に就き、イスラエル王国が建国され、その息子ソロモン王によって大いに栄えました。紀元前928年にソロモン王が死んで、その直後に王国は南北に分裂。北イスラエル王国は、紀元前721年にアッシリアによって滅亡。残った南ユダ王国ですが、新バビロニア帝国により紀元前587年に滅亡させられます。
新バビロニア帝国軍によって、エルサレム神殿をはじめ、南ユダ王国各地はことごとく破壊されたのです。この事態は単なる敗北と破壊に留まりませんでした。南ユダ王国の上流階級や聖職者、職人など、そのまま残しておくと国を再建するであろう人材や、新バビロニアで利用できるであろう人々は拉致され、バビロンに連れ去られるたのです。これをバビロン捕囚と呼びます。実に三千人以上の有力者たちが、新バビロニア帝国の首都バビロンの郊外へと連れ去られました。
* * * * * * * *
直線距離で400キロ以上も離れている異国に連行され、そこでの生活と働きを強要され、一方では「お前たちの神はどこにいる。その神は、お前たちに何をしてくれるのだ」と馬鹿にされ、嘲られる、こうした時代が60年も続いたのです。イスラエル民族と宗教は、歴史の中に消えていく、そんな運命下にありました。
しかし、イスラエルの人々は、困難さの満ちていた捕囚地にあって、自らの民族性と宗教性を失うことなく保持し、苦難の年月を生き延びたのです。
当初、人々は短期間で解放され、祖国復帰が実現するものと思っていました。しかし、人々の思いに反し、捕囚は約60年に亘って続いたのでした。
最初の世代の人々は、年を重ね、異教の地に死んでいきました。捕囚地で生まれた第2世代。世代が代わる中で現実の理解は変化していきます。捕囚を当たり前のように思う人が増えていき、帰還の祈りや願いは次第に薄れていきました。
長く異教の地に留め置かれ、人々の宗教観も変化していきます。神ヤハウェは一向の我々を救ってくださらない、エルサレムの神殿崩壊と共に、神ヤハウェも消滅したのだ、そんな感覚を持つ者が増えていきます。異教に惹かれる者も多くあり、イスラエルの宗教を保持し続けることも難しくなっていきました。
大方の人々がそうであっても、一部には違った考え方、信仰を抱く人々も残されました。イザヤやエレミヤなどの預言に励まされ、神殿祭儀によって成り立っていた礼拝を、言葉による礼拝に切り替えて、詩編や父祖の物語を編纂して礼拝で用い、宗教的伝統を状況に照らして改変しながら保持した人たちがありました。
○希望としての「光」
このような人々の業の中に生み出され、バビロン捕囚の苦難に喘ぐ民たちを強く支えたのが、今日の聖書のみ言葉でした。「地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は言われた。『光あれ』。こうして光があった。神は光を見て、良しとされた」。これらの語り・言葉は、長引く捕囚に絶望へと至ろうとしていたイスラエルの民たちに、神ヤハウェにある確かな希望を伝え、彼らを異国の地にあって支え続けました。
混沌(カオス)の最中、神は「光あれ」と語られました。「光」には、様々な理解がありますが、この言葉が編まれたバビロン捕囚という現実を踏まえて、神ヤハウェにある「希望」が「光」と語られていると受けとめたいと思います。
岩波訳の聖書では、ここに語られている「光」に註がつけられています。そこにはこう書かれています。「光は生命と秩序と救いの根源の象徴」。この註に従うならば、何らの希望も見出せないようなカオスの状態であっても、神は「光あれ」という言葉をもって、生命と秩序と救いの根源を据えられる、闇や絶望にも確かな希望が新たに創造される、そのようにこの箇所は語り継いでいるのではないでしょうか。
混沌に対して、神は「光あれ」と語られ、光が創造されました。続いて、4節を見ていただくと、そこには「神は光を見て、良しとされた」とあります。
* * * * * * * *
「良しとされた」、これは確実に神の御心がなったことを喜ぶ、そんな語りだと言われます。ある人は、その出来映えに感動する心の動きが表現されていると解説していました。神に創造された「光」は、混沌と闇に喘ぐ人々の指針となり、彼らを支えるに充分なものであったということでしょう。
このように、「光」は絶望的で混沌とした「闇」の中に神によって創造されました。絶望は絶望のままに終わらない、イスラエルの民たちは、自らを愛し、導き、支えてくださる神は、自分たちを包んでいる闇にも勝利し、ここからも必ず新しい希望を造り出してくださる、それが「光あれ」という神の言葉を生んだ、バビロン捕囚期にあって、神ヤハウェを深く信じ続けた人々の、一つの勝利宣言であったと学びたいと願います。
* * * * * * * *
こうした希望は、バビロン捕囚に直面した預言者たちによっても語られました。
招詞とした「イザヤ書」。捕囚期の末期に活躍した第二イザヤはこう預言していました。43章1節、「ヤコブよ、あなたを創造された主は イスラエルよ、あなたを造られた主は 今、こう言われる。恐れるな、わたしはあなたを贖う。あなたはわたしのもの。わたしはあなたの名を呼ぶ」と、捕囚の民たちに向けて、創造主なる神の贖い、元の状態へ買い戻してくださる恵み・愛が語られています。
4〜5節で「4わたしの目にあなたは価高く、貴く わたしはあなたを愛し あなたの身代わりとして人を与え 国々をあなたの魂の代わりとする。5恐れるな、わたしはあなたと共にいる。わたしは東からあなたの子孫を連れ帰り 西からあなたを集める」、苦難の中にある一人ひとりを神がどう受けとめておられるのか、今、捕囚をはじめ、祖国崩壊でちりぢりになってしまっている民たちを再び結集する、その希望が語られています。
○「最後まで、信仰のともし火を掲げましょう」
先週、ある方が「この文章をぜひ」と雑誌『婦人の友』の2007年1月号を持ってきてくださいました。ぜひと言われましたのは、「聖書・呼びかける言葉」のコーナーに記されていた晴佐久昌英神父の文章でした。
この号を、晴佐久神父は「みこころが行われますように」という題で、ご家族、ご両親のことを記しておいでです。これは、お母様が75歳で天に召され、その一週間後に記された一文です。
熱心なカトリック信者として歩んだ父母、その下に生を受けたこと。青年期に父親を天に送り、彼の信仰を受け継ぐ形で神学校に進んだこと、母親は75歳まで生を許されたけれども、その人生は幾多の試練、特に晩年は12回にも及ぶ手術の連続であったこと。舌の癌(舌癌)の痛みに耐えながら、最後は修行僧のように日々の治療を受けていたが、一気に容態が悪化、急に召天されたと記されています。
お母様の召天からしばらくして、友人がそのお母様から届いた手紙を晴佐久神父のもとに持ってきてくれたとのこと。友人は悩みを神父のお母様に相談していたとのこと。それは、召天の僅か二週間前に記された手紙でした。文中に、この手紙の最後の部分が引用されています。その一部をお読みします。
“私は、今回の手術の痛みがとれず、痛み止めを飲み飲みの生活で、食べるのが苦痛です。人は、痛みとかつらさに負けそうになりますね。私はほんとうに弱いですから、いつも悲鳴を上げて、イエスさま、マリアさま、ヨセフさま!と叫んでいます。でも、そんな弱い自分そのままでよいのだと認めるところから、いつも出発です。誰にも代わってもらえませんしね。最後まで、信仰のともし火を掲げましょう”。
説教の準備を進める中で、触れることを許されたこの文章。晴佐久昌英神父のお母様が、召天の二週間前、末期の激しい痛みを抱えている中に、悩みある者のために執り成し、書かれた手紙、そうした行動にももちろん感動しましたが、特に激しい痛みや苦しみの中で、「最後まで、信仰のともし火を掲げましょう」と自らを、そして悩める者を励まし記された、この言葉に深く深く打たれました。
バビロン捕囚という苦境の最中、イスラエルの人々が掲げ、自らと仲間たちとを励ましたのも、まさに「信仰のともし火」でした。そうした彼らの真実な信仰が、確かな希望の出来事としての神による「光」の創造に結実しました。
○神は必ず共にあって「光」=希望を
「創世記」はこう語り出されていました。「初めに、神は天地を創造された。 地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は言われた。『光あれ』。こうして光があった。神は光を見て、良しとされた」。これらの語りが、苦難の只中での尽きることのない希望を宣べ伝え、人々の確かな信仰の証となったのです。
私たちもそれぞれに、苦しみや痛み、病などを経験します。それは時として非常に破壊的であり、無秩序であり、闇や混沌としか表現できないものであります。しかし、どうしようもなく、逃れようのない、その闇や混沌にも、神は私たちと必ず共にあって、「光あれ」と希望を創造してくださる、この恵みの実感の内に、「最後まで、信仰のともし火を掲げ」つつ、進むことができればと願います。