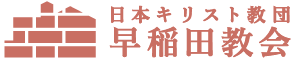説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2020年6月21日
「実体を伴った“ことば”」 ヨハネによる福音書1:1〜18
古賀 博牧師
〈聖書〉ヨハネによる福音書1:1〜18
| (1)初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。(2)この言は、初めに神と共にあった。(3)万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。(4)言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。(5)光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。 (6)神から遣わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。(7)彼は証しをするために来た。光について証しをするため、また、すべての人が彼によって信じるようになるためである。(8)彼は光ではなく、光について証しをするために来た。(9)その光は、まことの光で、世に来てすべての人を照らすのである。(10)言は世にあった。世は言によって成ったが、世は言を認めなかった。(11)言は、自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。(12)しかし、言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。(13)この人々は、血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。 (14)言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。(15)ヨハネは、この方について証しをし、声を張り上げて言った。「『わたしの後から来られる方は、わたしより優れている。わたしよりも先におられたからである』とわたしが言ったのは、この方のことである。」(16)わたしたちは皆、この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上に、更に恵みを受けた。(17)律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。(18)いまだかつて、神を見た者はいない。父のふところにいる独り子である神、この方が神を示されたのである。 |
|---|
今日は「ヨハネによる福音書」の1章18節までを読んでいただきました。
「ヨハネによる福音書」は紀元後の90年代に、ヨハネ教団において成立したと考えられています。この福音書は、マルコ、マタイ、ルカの三つの福音書とは別系統の資料を用いて編纂されました。
マタイ福音書やルカ福音書はそれぞれにイエス・キリストの誕生物語を叙述的に記しています。今日のヨハネ福音書には、マタイやルカのような物語としてのクリスマスは記されていません。しかし、実に独特な形での「クリスマス証言」、これをヨハネ福音書はその冒頭に置いて福音書を書き出しています。それが今日読みました1章の1節から18節まで。通常、この箇所をヨハネの「ロゴス賛歌」、あるいは「ロゴス・キリスト賛歌」などと呼んでいます。
1章の1〜3節にこうありました。「初めにがあった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった」。
「初めに言があった」、この「」にはロゴスというギリシャ語が用いられています。ヘレニズム文化で栄えたストア哲学の中心概念であったロゴス。このロゴスという用語でもって、「ヨハネによる福音書」はキリストを表現しました。
ロゴスであるキリストは、原初から存在しており、神そのものであったこと、キリストは最初から神と共にあり、このキリストにより全てのものは創造され、キリストによらずに成ったものは何一つなかった、このように神と等しきキリストが高らかに賛美されています。
そしてこのロゴスは単に言葉というのではなく、出来事をも表し、またこの世界の法則や道理という意味も持っています。「ヨハネによる福音書」は、冒頭にロゴスということを語り、この言葉でもって、世界の真理としてのキリスト、キリストの出来事をこそ証しようとしているのです。
今日の箇所に繰り返し登場する「ことば」、これに訳語として「言」という漢字一字があてられています。前にも語りましたが、このことの意味を考えたいと願います。
通常「ことば」とは「言」に「葉」をつけて「言葉」というふうに表記します。ところがここでは「言」の一字のみです。原初、「ことば」は「言」の一字で表していたとのこと。「言」は「事」と同じ意味を持ち、「言」は事実や事柄にもなり得る、そのような重い意味を持つものとして「言」と記されたのだそうです。漢字一字の「言」にはそのような「ことば」が本来有していた重さが表現されています。
しかし、現実的には「ことば」にそんな実質が必ずしも伴っている訳ではありません。それは私たちが用いている「ことば」を踏まえるならば明らかではないでしょうか。自分の「ことば」は一向に事実や事柄になり得ていません。古代日本人もこの事実を受け入れて、「言」にもう少し軽い意味も持たせようと、「端」の字を加えて、「言の端」「言端」としてこの語を用いるようになっていったというのです。
現在一般的な「言葉」は平安時代の『古今和歌集』の仮名序が起源だとのこと。撰者の一人・紀貫之の和歌から導いて、「言の葉」「言葉」とされたそうです。次第に「ことば」は「言端」ではなく「言葉」と記されるようになり、人の口から発せられたものが「葉」として散っていくようなイメージで理解されるようになります。
原初は「言」一字であったものに、「端」や「葉」が付けられ、少し軽い「言の端」となり、さらにはらはらと散る「言の葉」となって、今日の「言葉」という語が確定してきたと考えられています。現在の「言葉」がどのように成り立ってきたのか、その背後には「ことば」に対する感覚・捉え方が反映されているようです。
それでは聖書ではどうでしょうか。神の「ことば」とは世界の原初から確固たるものと存在しており、神の「ことば」がこの世界において確実に出来事となり、事態の意味をも明らかしていくと考えられています。こうしたことは、「創世記」の天地創造物語においても明らかです。混とんとし、深い闇に覆われていたこの世界に、主なる神が「光あれ」と「ことば」を発してくださったことで光が生じ、天地万物が次々に神の「ことば」によって創造されていきます。
旧約聖書の世界観を継承した新約聖書、キリストそのものが「神のことば」なのだと理解し、ヨハネ福音書の冒頭に記したのです。「初めに言があった」の「ことば」に「言」の一字があてられているのは、第一には聖書の語る「ことば」の重みを捉えのことであり、それに加えて日本語の変遷を遡ってのことでありましょう。
キリストこそが「ロゴス」(言)と語る文脈に置かれている14節前半に注目したいと思います。そこに「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」とあります。
「宿られた」と訳されている言葉は、「住まう、幕屋を張る」という意味を持つスケーノーというギリシャ語で、岩波訳聖書はここを「幕屋を張った」と訳しています。
旧約聖書の「出エジプト記」の25章に幕屋建設の指示が証言されており、25章8節に「わたしのための聖なる所を彼らに造らせなさい。わたしは彼らの中に住むであろう」と神の言葉が残されています。このように「幕屋」とは神の聖なる場所であり、「会見の幕屋」という呼び名もあるように、「幕屋」には神が宿っておられ、そこで神とお会いし、み旨を伺うための礼拝施設でした。後の神殿の原初の形態が「幕屋」ですが、出エジプトの脱出の旅において、民たちの内、礼拝に関わるレビ人たちによってこの用材や部品が持ち運ばれ、民たちが宿営する場所には必ずこの「幕屋」が張られ、神への礼拝が捧げられ、神が常に共にいてくださることを証していました。
「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」とは、「言」そのものである神の独り子イエス・キリストが私たちの間に幕屋を張ってくださったこと、「言」である主イエスは私たちの身近に歩み寄り、共に生きてくださったと語り継いでいます。
主イエスは、神の独り子でありながらも、高みに留まって人間をされたのではなく、私たちの間に、私たちと同じの弱き肉体を纏って住まわれ、人間の痛みや悲しみをつぶさに経験しつつ共に生きて、そうした地上での歩みを通じて神の愛を宣べ伝えてくださいました。そして、ついには苦難をも味わい、十字架に架けられ、血を流しつつ苦しみ、私たちの罪を贖うために命を捨てられたのでした。こうした主イエスの受肉の重みと恵み、その人生が「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」という証言には深く語り込められています。
一月ほど前(5月19日)の『朝日新聞』の朝刊の「折々のことば」の欄に、作家・井上ひさしさんの言葉が短く引用されていました。“名と実体との絶え間のない追っかけごっこが『生きている』ということではあるまいか”というものでした。
この言葉だけでは、今一つぴんとはこなかったのですが、この言葉が生み出された背景について、鷲田さんが井上ひさしさんの少年時代の体験に触れていらっしゃったのです。それを読んで原文に触れたくなり、初出として示されていた『社会とことば』(岩波書店)というエッセイ集を入手しました。
井上ひさしさんの幼少期、作家志望であった父親が病死し、母親は再婚。その再婚相手から虐待を受けたひさし少年は、仙台にあるカトリック系の孤児院「光が丘天使園」へと送られたのでした。そしてこの孤児院にて、院長を務めていらしたサルト・ベランジェというカナダ人修道士との出会いへ導かれます。
彼の暮らした孤児院は進駐軍のキャンプ近くに建っており、修道士たちの執り成しとキャンプの司令官の温情によって、日曜日にはアメリカ兵たちの食べ残した食物を、軍の食堂に入り込んで漁ることが許されていたというのです。極めて飢えていた子どもたちは、一週間分をお腹をこわすほどに喰い溜めしたとのこと。
ひさし少年はその時に初めて、ある雑誌で読んで知っていたアイスクリームというものと出会い、これがあのアイスクリームなんだと大きな興奮を憶えます。その際、ベランジェ修道士が次のようなことを語られたというのです。
私たちが生きるというのは、ただ名前や言葉として知っているものの実体と、いろいろな機会に出会っていくこと、生きていく中で、知っている名前や言葉と実体がしっかり結びついた時に私たちは仕合わせを感じると語られたというのです[註1]。
こうした語りから、ミサの真理は神の御名を覚え、その名前が実体と合致すること、まさにそれを表すこそが最高の仕合わせなのだ、と修道士は論を展開します。しかし少年たちは先生の十八番(おはこ)が始まったと聴き流していたというのです。
※[註]と付した下線部分は著作権に絡んでの要約です。原文は最後に示しています。
さて、ある時、いつものように食事を漁っていたら、そんな子どもたちを苦々しく思っていた若い兵士が拳銃を天上に向かって発砲したというのです。間もなく朝鮮半島に送られることになっていた兵士で、ストレスが頂点に達していたのであろうとのこと。驚いて泣き始めた少年に、興奮したその兵士は銃口を向けたそうです。
大声で何かを喚きながら、若いアメリカ兵が泣いている子に拳銃を向けたその時、ベランジェ修道士は静かに席を立って、その兵士の前に進み出て、銃口の真ん前に立ち、泣いているその子を庇ったとのこと。そんな修道士の姿を見て、これまで公教要理の時間にベランジェ修道士が繰り返し語っていたキリストの愛、「キリストは全人類を不幸のどん底から救おうとして命を投げ出されました。これがすなわちキリストの愛です」との教えの意味、その実質に気づいたと記されています。十字架の上に示されたのが神の愛の真実だなんて言っても単なる「言葉」だ、その実質はさっぱり判らない、そう思って子どもたちは冷やかに笑っていたというです。でも、神の愛、キリストの犠牲の実質・実体が、その時、いきなり目の前に現れて、名と実体、言葉と実体が一つになった、この時の感動に押されて、その年、多くの子どもたちが受洗したとのこと。ひさし少年もその一人だったというのです[註2]。
このようなことを井上ひさしさんの本で読んで、私は「ヨハネによる福音書」の語り継いでいる「言」の真実、1章14節の「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」に証された恵みに改めて想いを馳せました。
主イエスは、自らの命を投げ出してまで神の愛を証し、私たちが神に背き続けるその罪のために十字架に命を捨ててくださいました。この主イエスの出来事をベランジェ修道士は“キリストは全人類を不幸のどん底から救おうとして命を投げ出されました。これがすなわちキリストの愛です”と説いたのです。
この修道士は、ただの「言葉」として、つまりははらはらと散っていく実質を伴わない空虚な内容を語ったのではありません。自らの語る「言」、そこに真摯で熱心な信仰の真実を伴わせたのです。その信仰が兵士の構える銃口の真正面に子どもの命を守るために立ちはだかる、そんな行動へと彼を導いたのではないでしょうか。
誰にでもできることではありませんが、この修道士の行動から実体を伴った信仰とはどんなものなのかを深く考えさせられます。何よりも自分の語っている「言葉」、今日の説教もまさにそうですが、これにどんな信仰の実体が込められているのか、深く深く反省しつつ、自らの信仰の姿勢を見つめなおさねばなりません。
招詞としました「ヤコブの手紙」1章22節に、「御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わる者になってはいけません」と勧められています。
神の「言」として、愛と贖いの実体を伴って私たちのもとにお出でになった主イエスに深く感謝しつつ、主イエスの福音にどう生きるのか、実体を伴った「ことば」を語り、信仰を真実に証する、そんな歩みへと進む者となりたいと願います。
[註1]〈原文〉
“そう、生きるということはつまりそういうことなのです。私たちはまず名前を覚えます、その正体がわからぬままに、です。やがてどこかで私たちはひょっこりとその正体をめぐり合います。名前と正体とがしっかり結びつくと、私たちはとても仕合わせになります。そういう仕合わせを探して歩くことが、私たちの一生というものなのです”。
[註2]〈原文〉
“発射音に驚いて泣き出した子どもがいた。若いGIはなにか大声で喚きながら、その子に拳銃を向けた。そのときぼくらはベランジェ修道士がナプキンをおいて静かに席を立つのを見た。そして彼はその子を庇って拳銃の真ん前に立ったのである。…公教要理の時間に、ベランジェ修道士は「キリストは全人類を不幸のどん底から救おうとして命を投げ出されました。これがすなわちキリストの愛です」と説いていた。キリストの愛。名前があるだけではないか。ぼくらは鼻の先で冷笑し、救世主の愛と受難の一生をお伽話のように受けとめていた。ところが、その実体がいきなり目の前、銃口の前にあらわれて名と実体がひとつになったのだ。その秋、高校生と中学三年生の大部分が受洗したが、むろんぼくもそのひとりだった”。