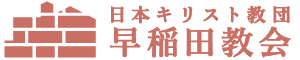説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2018年7月1日
「重たい言(ことば)」 ヨハネによる福音書 1:1〜5
古賀 博牧師
〈聖書〉ヨハネによる福音書 1:1〜5
| 1:初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。2:この言は、初めに神と共にあった。3:万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。4:言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。5:光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。 る。 |
|---|
○ヨハネによる福音書の冒頭部分
今日は、ヨハネによる福音書の1章の18節までを読んでいただきました。この箇所は、言うまでもなくヨハネ福音書の冒頭部分で、独特な表現での証言ですので、良く知られている箇所でもあります。
* * * * * * * * * * * *
ヨハネによる福音書は90年代に、ヨハネ教団にて成立したと考えられています。ヨハネ福音書より先に成立していた三つの福音書(マルコ・マタイ・ルカ福音書)の存在を知りながら、それらを下敷きにするのではなく、別系統の資料や姿勢の下にして、ヨハネ教団という場で信仰を共有している者たちによって編纂されたのであろうと考えられています。
* * * * * * * * * * * *
マタイ福音書や、ルカ福音書にはそれぞれに叙述的なイエス・キリストの誕生物語、所謂「クリスマス証言」というものがあります。今日のヨハネ福音書の冒頭、これは独特な形での「クリスマス証言」です。通常、これをヨハネの「ロゴス賛歌」、あるいは「ロゴス・キリスト賛歌」と呼んでいます。
1〜3節にこうありました。「1初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。2この言は、初めに神と共にあった。3万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった」。
「初めに言があった」、この書き出し部分、「言」にはロゴスというギリシャ語が用いられています。ヘレニズム文化で栄えたストア哲学の中心概念であった「言」(ロゴス)。このロゴスという語でもって、ヨハネによる福音書はキリストを表現しました。
ロゴスであるキリストは、原初から存在しており、神そのものであったこと、キリストは最初から神と共にあり、このキリストによって全てのものは創造され、キリストによらずに成ったものは何一つない、このようにこの箇所ではキリストが高らかに賛美されています。最初からあったキリスト、これを「先在のキリスト」とも表現します。「先在のキリスト」というのは、キリストは人間世界にイエス・キリストとして受肉し、身体をもって降誕する前から永遠に存在していた、と考えての教えです。
そして、この「ロゴス」は、単に言葉というのではなく、出来事をも表し、またこの世界の法則や道理という意味も持っています。そうしますと、ヨハネ福音書は、「ロゴス」という言葉を冒頭に置いて、この言葉でもって、世界の真理としてのキリスト、キリストの出来事を証しようとしているのだと理解できます。
○創世記の「天地創造物語」との関連
さて、ヨハネによる福音書の冒頭の語りは、旧約聖書の創世記の「天地創造物語」を背景に置いて書かれたのであろうと言われます。
今日の招詞とした創世記1章3節、「天地創造物語」の最初にこのように証言されていました。「神は言われた。『光あれ』。こうして、光があった」。
神が「光あれ」とことばを発せられたことで、混沌の世界に「光」が創造されたというのです。バビロン捕囚という苦境の中で、神による新しい希望の創造の祈りと期待とが、「光あれ」という一句に響いていることを以前に学びました。
創世記1章3節の「神は言われた」には、ダーバールというヘブライ語が使われています。ヘブライ語のダーバールは、「言う」、あるいは「言葉」を表しています。ダーバールは、単に意志伝達の道具としての「言葉」ということだけではなく、「事柄」や「出来事」を、またさらに事柄・出来事の「意味」や「解釈」という含みまで持っている特別な語です。イスラエルの人々は、この世に起こる事物や出来事の背後には、必ずダーバール(言葉、意味)があると考えていたのです。また、このダーバール(言葉、意味)が、新たな「事物」や「出来事」を生じさせたり、引き起こしたりするのだと考えられていました。
「神は言われた。『光あれ』。こうして、光があった」と、まさに神のダーバールによって光が創造されています。ただ「言葉」が発せられたというのではなく、ダーバルによって、混沌に新たな「出来事」が生起し、「光」が創造された、これは秩序、希望を「意味」し、また秩序、希望と「解釈」することができます。このように神のダーバール(言葉)が創造の業を導いていきました。
ヨハネによる福音書の1章1節、「初めに言があった」にはロゴスというギリシャ語が用いられ、「言」という一字が当てられています。ヘブライ語のダーバールに重ねるように、この福音書はロゴスと記しました。
天地創造の業において、「光あれ」という神のことばが光を創造し、混沌の世界に新しい希望と秩序とを生起させたように、神のことばは必ず出来事を伴うこと。この神のことばの力が、この世界にさまざまな出来事を生起させていくこと。神のことばは決して空しく終わることがないこと。このような信仰の証が、「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった」という語りには強く込められているのです。
○所詮は人間の言葉
ヨハネ福音書の書かれた90年代に、ユダヤ教の指導者であるラビたちが集まって、「ヤムニア会議」と呼ばれている会合が開催されました。
70年のユダヤ戦争によって、エルサレム神殿はローマ帝国によって破壊され、これからどうするべきかが話し合われ、ファリサイ派が中心となって、律法を重んじての礼拝と生活を組み立てていくことが決議されます。
この会議で、キリスト者をシナゴーグから追放することも決められ、以後、ユダヤ教、及びローマ帝国による迫害にキリスト者は直面していくこととなります。
ヨハネによる福音書は、こうした迫害、また異端との論争という過酷な環境の中で編集されていきました。
多くの誹謗中傷の言葉が、キリスト者たちには容赦なく浴びせかけられ、場合によってはその命までが狙われました。しかし、ヨハネ教団の人たちは、どれほど酷い非難の言葉を浴びようとも、また危険な目に遭おうとも、それらは所詮人間の言葉・行いだと心に刻んだのです。自分たちを嘲り、蔑む言葉、またそれらを伴う行為がいかに酷く、重大なものであっても、それらは全て人間の業、限界を持っており、神のことば、キリストの真実とは違っている、この確信の表明として、ヨハネ福音書の冒頭は書き記されたのだと言われます。
こうしたあり方は、バビロン捕囚の中で、天地創造の物語を編んでいった紀元前6世紀のイスラエルの人々の想いや信仰と深く響き合っています。
○「言」一字で
さて、今日の聖書箇所を見ていただきますと、「ことば」には「言」の一字があてられています。通常、言葉というと「言」に「葉」がついていますが、ここでは「言」の一字のみで表現されています。
原初、「ことば」は「言」の一字で表していたとのこと。「言」には「事」と同じ意味があり、「言」は事実や事柄にもなり得るという意味を持っていたというのです。この「言」に事実を伴わない、少し軽い意味も持たせようと「端」を加えて、「言の端」、「言端」として用いられるようになっていきます。
「葉」を用いた「言の葉」は、平安時代の『古今和歌集』のその仮名序が起源だと言われています。『古今和歌集』の撰者のひとり、紀貫之が「やまとうたは ひとのこころをたねとして よろづのことの葉とぞなりける」(和歌は人の心を種として、芽吹いた木にさまざまに言葉の葉が繁ったようなものである)と記したことに発し、「言の葉」「言葉」として定着したとのこと。次第に「ことば」はこの「言葉」と記されるようになり、人の口から発せられたものが「葉」として散っていくイメージでも理解されるようになったということです。
原初は「言」一字であったものに、「端」や「葉」がつけられて、少し軽い意味の「言の端」となり、はらはらと散っていく「言の葉」となって、今日の「言葉」という漢字や語が確定してきたのだそうです。こうした性質を、人間の用いる「言葉」は持っている、このように日本語の変遷の中では捉えられてきたようです。
しかし、「神のことば」とは厳然と存在し続け、出来事となり、事態の意味をも明らかしていく、そして何よりもキリストそのものが「神のことば」なのだと、ヨハネ福音書は証言しています。「初めに言があった」との書き出しは、たぶんこうした漢字の変遷も踏まえて「言」一字となっているのではないでしょうか。
軽い「言葉」に満ちている現在です。政治家や官僚たちの言葉、ネットやSNSに飛び交う言葉も実に軽く、内実を伴っていないことを感じさせられます。
○心を揺さぶり、動かす〝ことば〟
一昨日、29日(金)の夕刻から、ここスコットホールで沖縄の基地問題に関する集会が開催されました。講演者としてお出でくださったのは、前の名護市長・稲嶺進さんでした。「稲嶺進・前名護市長を迎えて、沖縄の基地問題を考える!沖縄『慰霊の日』を心に刻んで」という集会、私も稲嶺さんの講演部分だけしたが、これに参加いたしました。
稲嶺進さんは、そのお話の中で、今年の6月23日に摩文仁で行われた「沖縄全戦没者追悼式」のことにも触れられました。この式に参列して、浦添の中学三年生の相良倫子さん(14歳)の「生きる」という題名の「平和の詩」朗読に深く心打たれたというのです。その詩の全文を資料として配付してくださり、後半に出てくる次の一節を朗読されました。
〝 私は、今を生きている。みんなと一緒に。そして、これからも生きていく。
一日一日を大切に。平和を想って。平和を祈って。なぜなら、未来は、
この瞬間の延長線上にあるからだ。つまり、未来は、今なんだ。〟
この言葉に導かれるようにして、名護市政からは一端離れた自分だが、ひとりのウチナーとして、沖縄の未来へと向かって、辺野古基地問題をはじめ平和の取り組みを諦めてはならない、今を大切にしなければならない、そう痛切に思わされたというのです。
少女の詩の朗読の後、内閣総理大臣から来賓挨拶を受けたとのこと。整えられた語りであったが、読み手の表情や声のトーンを含め、その言葉は何一つ心に響かず、頭の中を素通りした、それは偏に語られている言葉が総理大臣の本心ではなく、官僚が整えたもので、それをただ読んだに過ぎなかったからだろう、こうした稲嶺さんの語りを、今日の説教準備の段階で印象深く伺ったのでした。
○神の「言」に聴きながら
形式的で心に届かない適当な説明や言い訳、自己弁護の繰り返し、時間の隙間を埋めているに過ぎない、そんな意味のない軽い「言葉」に満ちている現在です。
こうした時代の最中であっても、またそういう時代だからこそ、私たちは聖書から神の「言」をしっかりと聴き、受けとめ続けていきたいと思います。
今日のヨハネによる福音書1章の語り、そして招詞とした創世記の証言、そのどちらもが極めて厳しい状況の最中に記されたものでした。絶望の淵に立たされ、嘲笑と罵倒、いのちの危機の中で、信仰者たちは神の「言」にこそ聴き、それを信頼し、神の「言」に立ち続けようとしました。この現実にも、必ず神は新たな出来事を「言」によって起こしてくださる、そしてその出来事に確実な意味と希望とを与えてくださる、そう信じ、生きた信仰者たちの歩みに、私たちもまた軽い言葉に流されたり、毒されたりすることなく連なっていきたいと願います。