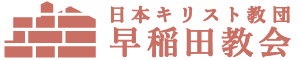説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2020年5月31日
「小さな筆」 使徒言行録 2:1〜4、ガラテヤの信徒への手紙5:16
古賀 博牧師
〈聖書〉使徒言行録 2:1〜4/ガラテヤの信徒への手紙5:16
| [使徒言行録2:1〜4] |
|---|
本日、私たちはペンテコステ(聖霊降臨日)の礼拝を迎えました。この礼拝を通じて、かつても今も豊かに働きたもう聖霊を受け、聖霊の風によって、それぞれの歩みへの励まし・後押しを受けたいと願います。
ペンテコステは「五旬節」(五旬祭)とも呼ばれ、これは元来、パレスチナにおける春の小麦の収穫祭でした。こうした農業祭に、ユダヤ教はモーセを通じて十戒(律法)が授与されたことを記念する日との新たな意味づけを行います。
巡礼を伴う祝祭であった「五旬節」には、新約聖書時代にさらに新たな意味が与えられます。それは、この日に主イエスの弟子たちに約束の通りに聖霊が降ったからです。聖霊の力を受けた弟子たちは使徒へと変えられ、広く世界に福音を宣べ伝えていきます。彼らの働きで各地に教会が誕生していきます。こうした福音宣教の開始と教会誕生の日として、ペンテコステは教会において大切にされてきました。
今日の招詞とした「使徒言行録」の1章8節にこのようにありました。
「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」。
こう主イエスがこう語られた時、弟子たちは、十字架上に主が処刑されたことから、従ってきた自分たちも罰せられるに違いないとひどく恐れて、エルサレムにひっそりと隠れ暮らしていたのです。そんな彼らのもとに現れてくださった復活の主イエスが語られたのが、先のみ言葉です。
人に知られないように隠れ、生き延びていた弟子たちは、エルサレムはおろか、ユダヤとサマリアの全土にまで出ていくことなど、想像すらできなかったことでしょう。彼らは、ただ主イエスの教えと思い出とを仲間内で静かに温め合めながら、周囲に自分たちの存在の気配を消して生きていたのです。
主イエスの昇天の10日後に迎えた「五旬節」のお祭り。その時、弟子たちは実に不思議な体験をします。「使徒言行録」2章1節以下にこう証言されています。
「五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした」。
聖霊が降臨し、その恵みと力に満たされることで、弟子たちは使徒へと変えられます。かつて復活の主が「エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」と語られた通り、彼らは隠れ暮らしていた家の扉を大きく開いて、外の世界へと果敢に歩みを進めていくことになります。
聖霊に与ることで背中を押され、それまで思ってもみなかった全く新しい証の歩みへと踏み出していく、聖霊の力を豊かに受け、聖霊により励まされ、導かれる者たちの姿というものをここに見て取ることができます。
私たちの国・日本へのキリスト教の伝来について、高校の日本史の教科書にこのように記されています。“1549(天文18)年、日本布教をこころざしたイエズス会(耶蘇会)の宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着し、大内義隆・大友義鎮(宗麟)らの大名の保護を受けて布教を開始した”。
ザビエルは1541年にリスボンを出発。アフリカを経由し、翌年にインドのゴアに到着、1545年にはマレーシアのマラッカに移り、このマラッカで鹿児島出身の日本人ヤジロウに出会って、日本への宣教を志すようになります。このようにヨーロッパからアフリカの喜望峰、インド、マレーシアを経由しての日本への8年の旅程。宣教師であるフランシスコ・ザビエルとその協力者たちによって、私たちの国にキリスト教が伝えられました。今から約500年前、1549年のことです。
当時のヨーロッパから見れば、間違いなく世界の果てであった日本、そこまで宣教師たちが到来し、キリスト教を伝え、神の愛とこれに応答していく慈愛の生き方を宣べ伝えたのです。このような事実を改めて考えると、招詞とした「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」とのみ言葉は、歴史を通じて真実なものとされていることを思わされます。
『守教』という小説があります。帚木蓬生さんの作品で、新潮文庫から上下巻で出ています。福岡県久留米市近くの小郡市の出身の帚木さんは、故郷を舞台とした「久留米藩三部作」に取り組まれ、この『守教』が三部作の最終巻となります。
『守教』は、室町時代の1569年から、明治維新直前の1867年までの約300年の間、福岡の片田舎に生き続けたキリシタンたちの歩みを追った歴史小説です。
作者はこの『守教』という小説について、出版元のインタビューにこう答えておいでです。
“普通の生活を送っている百姓や庄屋たちが、キリスト教にどのようにして出会い、受け入れ、それによって日常がどう変わったのか。私は、今まであまり取り上げられてこなかったその部分を、しっかりと書いておきたいと思いました。もう一つ、隠れキリシタンが福岡にもいたという事実を書き残しておきたかったのです”。
福岡県三井郡大刀洗町もある、殉教者の墓の上に建つカトリック今村教会に繋がっていく長大な物語なのですが、これに強く惹きつけられて、一気に読んでしまいました。
小説を読みながら、キリシタンたちの抱く、素朴でありながらも、実に真摯で揺るぎのない信仰に強く心を打たれました。キリシタンたちは、パードレと呼ばれた神父やイルマンという修道士、そして同宿と呼ばれた見習い修道士たちから伝え聞いた、数少ない聖書の教えを自分と家族や村の中でしっかりと保ち、実生活の倫理と規律を整え、慈悲の想いを村の人々との関わりに活かし、農作業に励んでいきます。
下巻の第7章は「宗旨人別帳」という表題、江戸時代、1660年代が描かれています。
「宗旨人別帳」は「宗門人別改帳」とも呼ばれ、江戸時代に町村ごとに作成し、領主に提出しなければならなかった、現在での戸籍台帳のようなものです。この作成と提出には、領地内の住民一人ひとりが自らはキリシタンでないことを証明するとの目的があり、そのために菩提寺による認証の印判も必要とされていたのです。
『守教』上巻の主人公である米助(後に久米蔵)。彼の二人の息子の内、次男・道蔵は周辺の村の庄屋に婿入り。大庄屋の兄・音蔵の治める多数の村々に存在するキリシタンたちを守るために、わざと兄に自分を告発させます。道蔵は捕らえられて拷問を受けますが、どうしても棄教しないため、ついには出身の村にて見せしめとして磔となり殉教します。下巻の表紙絵は、その場面を描いたものです。
その後、「宗旨人別帳」の提出が求められ、殉教者の長男で庄屋を継いだ鹿蔵は、村人たちのために菩提寺を初めて訪ね、老僧・円仁と出会います。殉教した父の墓に、この僧が手を合わせているとかねてより耳にしていた鹿蔵。
この際、鹿蔵はかつて父が寺を訪ね、村のこれから、いずれ皆がお世話になるからと頼んでいたと聞き、驚きます。円仁はかつての道蔵との話を思い起こし、このように道蔵の言葉を取り継ぎます。
“「自分を、神の手の中の小さな道具にする。私たちは、デウス・イエズスの筆先に過ぎません…今村の百姓は皆が神の筆先ち思ってる」。…今村の田畑に実る見事な作物は、その結実だったと思い至ったこつです…百姓たちのひとりひとり、そして私どものひとりひとりが、大河の一滴、小さな筆先…”。
これは一族に口伝されてきた信仰の実感でもありますが、神の子イエスの筆先として生きる、この決意と祈りの込められているた語りに、深く心を打たれました。
イエス・キリストを信じ、神の筆先として、実生活を通じて信仰を具体的に証しながら生きる、ただ口先でそう言うのではなく、日々の農作業を誠実にこなし、村の共同作業に喜んで奉仕し、没落した農民を受け入れ、間引きされた乳飲み子を誰かが引き取るなどなど。この村の人々は、主の福音と神の愛とを実生活へと活かして歩み、強まっていく禁教政策による迫害の荒波の只中にも、密やかに信仰を保ち、村の内にそれを継承し、明治時代直前までをひたすらに隠れ潜みながらも、極めて具体性をもった信仰の証に実に静かに静かに生き続けていくのです。
「ガラテヤの信徒への手紙」5章16節にこのように語られていました。
「わたしが言いたいのは、こういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません」。
『守教』という小説を読みながら、「霊の導きに従って歩みなさい」とのパウロの勧めが深く心に響いてきました。パウロは重ねて語っています、「そうすれば、(つまりは聖霊に導かれて歩むならば)決して肉の欲望を満足させるようなことはありません」。小説の中であった“私どものひとりひとりが、大河の一滴、小さな筆先”という言葉、そして具体性をもってこの信仰をこそ証しながらの生き方は、この世の、また自分の内に根深い「肉の欲望」に従ってのものではなく、神の御心にこそ突き動かされたもの、まさに聖霊の導きによるものではないでしょうか。
今年のペンテコステ、一人ひとりが、聖霊の導き・後押しを祈りを強くして、その場にあって受けたいと願います。聖霊を受けてのその後は、聖書に証言されているような経過とは違ったものになろうかと思います。かつての使徒たちは共に集まっている家にて聖霊降臨を経験し、聖霊の後押しを受けて、その家を出て、多くの人々と触れ合いながら、主イエスの福音を宣べ伝えました。このあり方とはまた違った方向への導きを、聖霊を一身に受けて今私たちは進みたいと願います。
緊急事態宣言が5月25日に首都圏でも解除されたとは言え、感染の危険に晒され続けています。そのため、兄弟姉妹と触れ合うことは未だ避けなければなりません。日と場所を決めて同信の者たちが一堂に会して礼拝を捧げ、主にある交わりを持ち、聖餐式を含んだ食事を共にする、初代教会の時代からずっと大切にされてきたこうしたあり方はしばらく為し得ません。そんな現実の最中に私たちは生きていきます。
『守教』が描いた潜伏キリシタンたちの生き方から深く学びたいものです。彼らは200年間、隠れ潜みながらも、日々、具体性を伴った信仰の証に静かに生き続けたのです。各自の生き方を伴った信仰の実質が、共に集ってミサを捧げることなくとも、家族に、村全体に穏やかに継承され、慈愛に満ちた関わりを形成し続けていきました。この事実に注目し、そこにも確実に働きたもうた聖霊の恵みを深く憶えたいと願います。
私たち一人ひとりも、神の、そして主イエスの「小さな筆先」です。「小さな筆先」であるからこそ、現在の試練・苦難の只中で、このペンテコステに聖霊の導き、そして後押しを、何より励ましを新たに、そして豊かに受け、この時に必要な示唆をいただきたいと思うのです。
説教の後に讃美歌54年版の270番を賛美しますが、1番にこう歌われています。
“信仰こそ旅路を みちびく杖 よわきを強むる 力なれや
こころを勇ましく 旅を続けゆかん この世の危うき 恐るべしや”
聖霊の励ましをしっかりと受け、この苦境の最中にも「こころを勇ましく (信仰の)旅を(信仰の生き方)を(それぞれの場で、離れていても心と祈りを繋げつつ、静かに、しかし確実に)続け」ていきたいと願います。