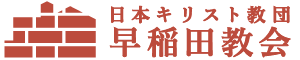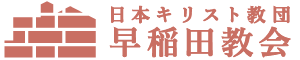説教
早稲田教会で語られた説教をテキストと音声データで掲載します。
2020年9月20日
「おろおろ」 ルカによる福音書 15:11〜24
古賀 博牧師
〈聖書〉ルカによる福音書 15:11〜24
| (11)また、イエスは言われた。「ある人に息子が二人いた。(12)弟の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言った。それで、父親は財産を二人に分けてやった。(13)何日もたたないうちに、下の息子は全部を金に換えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。(14)何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。(15)それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。(16)彼は豚の食べるいなご豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人はだれもいなかった。(17)そこで、彼は我に返って言った。『父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどパンがあるのに、わたしはここで飢え死にしそうだ。(18)ここをたち、父のところに行って言おう。「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。(19)もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください」と』。(20)そして、彼はそこをたち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。(21)息子は言った。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません』。(22)しかし、父親は僕たちに言った。『急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。(23)それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。(24)この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ』。そして、祝宴を始めた。
|
|---|
本日は「ルカによる福音書」15章から、「放蕩息子の譬え」を読んでいただきました。
この譬えの概要を共に振り返っておきたいと思います。ある人に二人の息子がありました。兄は忠実に父親に仕えていましたが、弟は父親がまだ存命であるにもかかわらず、その財産の分け前がほしいと願ったというのです。当時、二人兄弟の場合、財産分与は兄が三分の二、弟は三分の一と定められており、父親の死後に分けられるのが常でした。ところが、この下の息子は父親がまだ元気であるのに財産分与を求めています。これは父親と完全に断絶するという宣言に等しいものでした。
こうした弟のあり得ない要求を父親はそのままの飲んだというのです。父親の財産の一部を受け取った弟は、数日の内に全てを金に換えて遠い国に旅立ちました。最初はこのお金で商売をして、身を立てようとしたのではないかと考えられています。しかし、そうした弟の頑張りのようなものに、主イエスは一切触れずに、「放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった」とだけ語っていらっしゃいます。
放蕩三昧で全てを使い尽くした時、ひどい飢饉が起こり、無一文の弟は、金を使っていた頃に付き合いのあった者たちの誰からも何らの憐れみも受け取れなかったようです。まさに「金の切れ目が縁の切れ目」ということでしょう。
生き延びるために彼は豚の世話を始めます。ユダヤ的な感覚では、豚の世話とは究極の屈辱。ユダヤ教の食物規定で豚は汚れた動物とされ、誰もこの家畜を飼う者はいなかったと言われていますので、異邦人の雇い人となったということでしょう。
ところが、働いても暮らしは立ちゆかず、日々の食事にも事欠く始末。ついには豚の餌であるいなご豆 — これは豆自体ではなく、その皮だったと言われます ー、そんな豚しか食べないような物を口に入れなければならない程に落ちぶれたというのです。それでいて誰からも顧みられることはなかったのでした。
17節に「そこで、彼は我に返って」とあります。自分の帰るべきところは「父のところ」だとはっきり見定めて、帰るための方策をさまざまに考えます。「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください」、こう言って憐れみを請い、何としても受け入れてもらおう、そのように考えて故郷へと帰っていきます。
この後に続く語りは何とも驚くべきものです。主イエスは、息子の方から見限られたあの父親の振る舞いを、弟息子が出て行った後にどうしていたのかをも含めて、20節の後半にこう語っています。「ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した」。
この父親は下の息子が出ていってからというもの、いつかはきっと彼は帰ってくると信じて、来る日も来る日も諦めることなく家の外に出て遠くを見つめ、下の息子が現れるのをずっと待ち続けていたということではないでしょうか。そして、ついに父親は下の息子の帰還を遠くに認めることができ、走り寄って迎えたのです。
「憐れに思い」とは、新約聖書で重要なキーワードです。相手の痛み・苦しみを思い、自らの内臓に同じ痛みを感じる、まさしく断腸の想い、こうした大きく深い心の動きを表現している言葉です。この「憐れみ」を通じて、神の愛が語られています。
自分を見限って捨てた者をも、いつ帰るかと外に立って待ち続ける、そして見つけたならば「憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻し」てと、心を込めて最大限に歓迎して迎え入れる、そんな父親を主イエスはここに語り継いだのでした。
この譬えに登場する誰に想いを寄せて話を味わっておいででしょうか。多くの人は、放蕩の限りを尽くした弟と自分を重ね合わせて、この譬えを読んでいるようです。
私はこの後に登場する兄の姿に自分を発見します。兄は忠実に父親に仕えていました。この兄は、父親が放蕩の限りを尽くして戻ってきた弟を歓待したことに腹を立て語っています。25節以下を読みます。「ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこで、僕の一人を呼んで、これはいったい何事かと尋ねた。僕は言った。『弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛を屠られたのです』。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出て来てなだめた。しかし、兄は父親に言った。『このとおり、わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、わたしが友達と宴会をするために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰って来ると、肥えた子牛を屠っておやりになる』」。
妙に真面目な面もあり、融通が利かず、実に頑なな私。弟の帰還を父親と共に喜ぶのではなく、父が自分を評価してくれないと腹を立て、弟を「あなたのあの息子」と他人のように表現し、あいつは「娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰って来」たとんでもない奴だと非難する、そんな兄に自分の真実が重なるのです。
医師として赤道直下のアフリカで長く働き、「密林の聖者」と呼ばれたアルベルト・シュヴァイツァーは新約聖書学者でもありました。彼は、神とはどんな存在であるかを考えるために「放蕩息子の譬え」に注目し、長く格闘してきたというのです。
シュヴァイツァーは、譬えの中心は放蕩した上で帰還した弟息子ではなく父親であるとし、この父親のことを「無能力な全能者」と呼びました。“(無能力な全能者である)彼は強制的な力を用いることもなく、待つことしかできません。燃えるような愛の心で待つ”、これがこの譬えに語られている父親だとのこと。
そして、シュヴァイツァーも兄に自らを重ねています。放蕩を尽くした弟、そんな彼を待ち続け歓待する無能な父親、そうではなく生真面目に仕え、忠実に働く兄の抱く高慢さの中に自分の本当の姿を発見し、そこから十字架の主の真実に目を凝らして、高ぶっている自ら、自分の不信仰を神の御前で切り裂こうとしています。
主イエスは“十字架に釘付けされ、磔刑に処せられ、手足を動かすことはもちろん、もはや地の上に立つべき場所をもたなかった”と彼は言います。この十字架のイエスに「無能力な全能者」である神の愛が証されていると語ります。こうした神とは“天上の喜びと権威に満たされた祝宴の広間に座しているのではなく、自分に背く息子に(家の)中に入るよう乞い願いつつ、冷え冷えとした暗い夕方、外に立っている”、そんな父親を通じて神の真実を描いているのが今日の譬え話だというのです。
神学者・小山晃佑さんは「『おろおろ』こそ神学の本質」と語られました。背後には彼の神観があることを思います。神と言えば厳格・毅然として揺るぎない存在で、人間の想いや行いに照らして審く、そんなお方だと思ってはないでしょうか。しかし、主イエスを通じて証されている愛の神は、毅然としただけの神ではなく、「おろおろ」する神であり、こうした神を発見し、御旨に推し量るのが神学の本質だと言うのです。
小山晃佑さんは『神学と暴力』(教文館)という本にこのように記されています。“一人の苦しむ人の前で、簡単にあきらめたり、見捨てたりするのではなく、真の神ならどうなさるであろうかとおろおろして迷い、考え、畏れをもって祈ることです。この『おろおろ』こそ神学の本質です”(P43)。この語りの背後には、キリスト教の神が「おろおろ」することもあるとの、この神学者の確信があることを思います。
時として「おろおろ」する神が、今日の譬えの父親を通じて証されているのではないでしょうか。あの弟息子をも見捨てることなく、いつ帰ってくるかと「おろおろ」しながら待ち続けている、この父親の姿から愛の神の真実を学びたいと願います。
熊本を舞台に文学や詩に取り組んだ石牟礼道子さん。『苦海浄土—わが水俣病』という作品で有名な方ですが、この作家はこのように語り残されました。
“ああ、あなた、悶え加勢しよるとね。そのままでよかですよ。苦しい人がいるときに、その人の前をただおろおろとおろおろと行ったり来たり、それだけでその人の心は少し楽になる。そのままでよかとですよ”。
この作家の言葉を紹介したある医師は、“ケアの世界ではしばしば「おろおろする」ことは「いけないこと」「プロとして恥ずかしいこと」と思われがちです。そして、おろおろしていることを悟られないようにしている内に、いつの間にか私たちは「おろおろする力」を失い、「おろおろすること」そのものを忘れてしまったのではないでしょうか。そこに、患者さんが楽にならない原因の一つがあるのかもしれません”と語っています。今日の学びに関連して心に刻むべき語りだと受けとめています。
今日は「放蕩息子の譬え話」から、キリスト教の神が、痛み苦しむ一人を見捨てることなく、愛し、待ち続けて「おろおろ」とする、そんな神の姿を学びました。招詞とした「迷い出た羊の譬え」にもこう語られています。「そのように、これらの小さな者が一人でも滅びることは、あなたがたの天の父の御心ではない」。小さな者である私、そして私たちの滅びを決して神は望んでおらず、迷い出た一匹としてどこまでも「おろおろ」しながら、探し出してくださいます。こうした神のあたたかな愛に心から感謝します。
こうした感謝をしっかりと胸に抱いて、小山晃佑さんが私たちに示す新たな課題へ向かって歩みを進めたいと願います。“一人の苦しむ人の前で、簡単にあきらめたり、見捨てたりするのではなく、真の神ならどうなさるであろうかとおろおろして迷い、考え、畏れをもって祈る”、さまざまな関わり・出会いの中でこうした祈りや取り組みへと進む、そんな信仰を求めていきたいと願います。